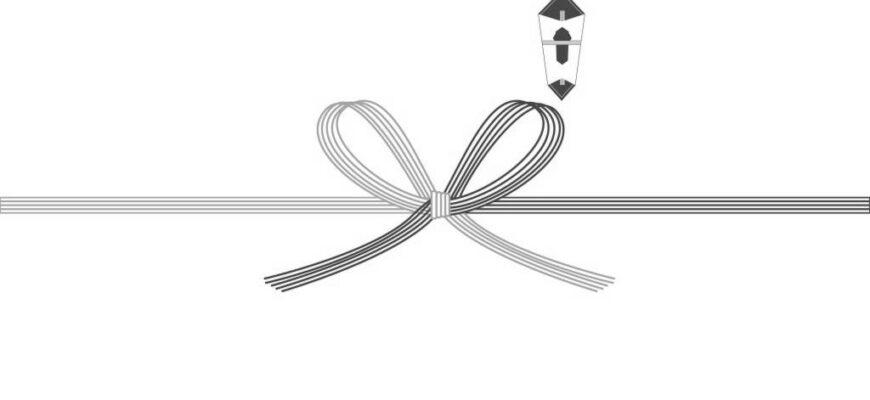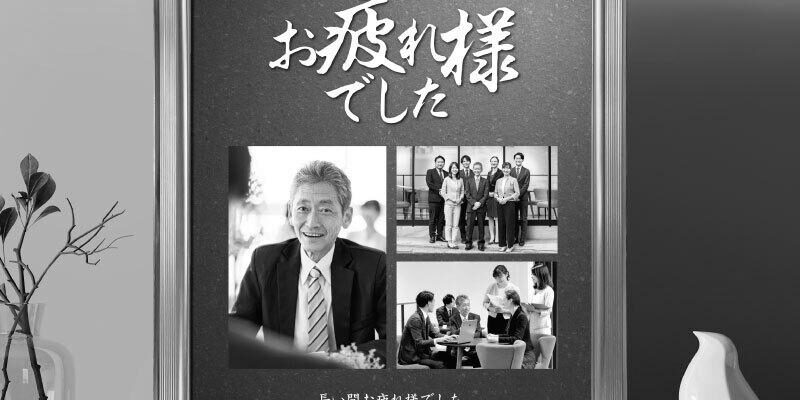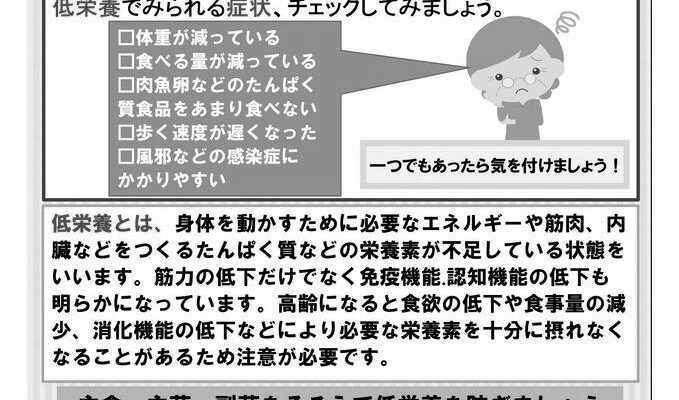event
お中元ってずーっと昔からある風習ですが、今は「お中元はいらない」と思っている人も多いです。 厄介な風習と感じている人が多いんですね。 正直めんどうくさいし、毎年負担になるし、「必要と思えないことは無理にしなくていい」という風潮が強い今の時代には合っていないということでしょう。 実際、アンケートによる「必要ないと思う日本の風習」のトップ1,2は、年賀状とお中元です。
敬老の日に財布をプレゼントをしようと考えているあなた! とっても優しいですね^^ その気持ちがあるだけで、とても素敵だと思います。 ここでは、敬老の日に贈る人気のレディース財布や二つ折り財布を紹介します。 お母さんやおばあちゃんへのプレゼントの参考になれば幸いです。 スポンサーリンク 目次 敬老の日にお財布を!人気のレディース財布は?
昔から「お中元」ってありますけど、これってどういうものか分かりますか? 結構あやふやに理解している人も多いんじゃないでしょうか。 私がそうなので^^; 特に詳しく知ろうともしないし、知る必要もないのであやふやになってることってあると思います。 お中元についても、詳しく知らずとも日常生活で困ること無く済んでいきますからね。
敬老の日って何かプレゼントをあげないといけないんでしょうか? 雑誌やテレビなどでも必ずのように特集があったりで、何かあげるのが当たり前のような…そんな圧力を感じる人もいると思います。 たしかに、お互いに良い関係が築けているなら喜んでプレゼントできますが、世の中そんな上手くいってる関係ばかりではありません。
敬老の日はいつから祝うものなんでしょう? 世間で敬老の日といえば、おじいちゃんおばあちゃんに感謝を伝えるということでプレゼントを贈ったりしていますが、「おじいちゃんおばあちゃん」ということは孫ができてからなんでしょうか。 でも、若いおじいちゃんおばあちゃんもいますよね。まだまだ若いと敬老の日に祝うというのは違和感がある気もします。
お盆は、先祖の魂が帰ってくる・亡くなった人たちが戻ってくるので、それをお迎えして供養する行事ですよね。 祖先のお祀り(おまつり)の習慣や昔の農耕儀礼、祖霊信仰や仏教など、いろいろと合わさって、現在のお盆となっています。(なので、地域差が大きい行事でもあります) で、ここで一つ疑問があります。 それは「先祖の魂が帰ってくるっていうけど、どこに帰ってくるの?」というものです。
お盆のお供えを、菓子折りなどの食べ物にするかお金にするか迷ったことありませんか? 「食べ物よりお金の方がいいんじゃないかな?」とか「でも、お供えにお金っていうのは失礼にあたるのかな?」とか。 で、「お金」でもOKらしいんで、お金にすることにしたものの… その場合どういう風に持っていったらいいのか、決まりごとみたいなものがあるなら事前に把握しておきたいって思いますよね。
お盆にお供えしたお供え物ってどうしてますか? その家庭や人によって処分の仕方が違ったりするんですよね。 後始末に悩んだりする人もいるんじゃないでしょうか。 そもそも「お盆のお供えはこう処理するものだ」という昔ながらのルールのようなものはあるんでしょうか。 昔は昔、今は今ですが、あるなら一応知っておきたいところです。
お盆には仏壇やお墓にお供えをしますが、そのお供え物っていつ食べるといいんでしょう? 菓子折りや果物なんかがよくお供えされてますよね。 お供えものを見て「あ、美味しそう」ってちょっと気になることもあります^^ お盆のお供えはいつになったら食べていいのか、いつからいつまでお供えしておくものなのか確認しておきましょう。
七夕と言えば7月7日。 誰もが知っていますよね。 七夕祭りなどのイベントもこの時期に開催されています。 ところが、地域によっては月遅れの8月7日前後に開催されていたりします。 七夕は7月7日なのに、不思議ですよね。 私は子供の頃から「七夕=7月7日」だと認識してきましたが、月遅れでやっている地域の子供なんかは8月7日が七夕だと認識してたりするんでしょうか。